 ヘルスケア
ヘルスケア 偏頭痛(片頭痛)の群発頭痛が再発した件。群発頭痛の原因は?自分に効いた薬を紹介します。
片頭痛の発症 今から10年ほど前に発症した片頭痛。そのあまりの痛みから、当時はMRIで頭の様子も見てもらったのですが異常はなく、原因は分からず終いでした。仕事中、この痛みに襲われた時には頭痛薬を飲んでトイレに駆け込みしばらくうずくまる、そん...
 ヘルスケア
ヘルスケア  DIY
DIY  ヘルスケア
ヘルスケア  ショッピング
ショッピング  DIY
DIY  DIY
DIY  ショッピング
ショッピング  ショッピング
ショッピング 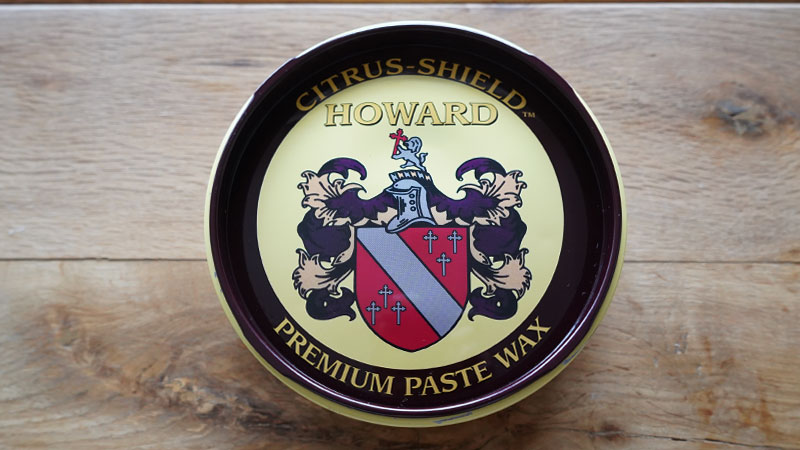 DIY
DIY  DIY
DIY